
「今年も赤字決算だった…これで3期連続赤字だ。」
「このまま会社はどうなってしまうのだろう? 融資はもう受けられない?」
「3期連続赤字から立ち直る方法はあるのだろうか…」
決算書を受け取り、「3期連続赤字」という現実に直面した経営者の皆様は、深刻な不安を抱えていることでしょう。「3期連続赤字 どうなる?」という問いは、会社の存続そのものに関わる切実な問題です。
一般的に、1期の赤字で要注意、2期連続で危険信号、そして3期連続となると、事業継続が極めて困難な状況にあると見なされます。
この記事では、ここ愛媛県をはじめ多くの中小企業の経営改善に携わってきたコンサルタントとして、なぜ3期連続赤字でも会社が存続できているのか(一時的な理由)、それが銀行の融資姿勢や取引先、従業員にどのような影響を与えるのか、そして経営者が取るべき選択肢について解説します。
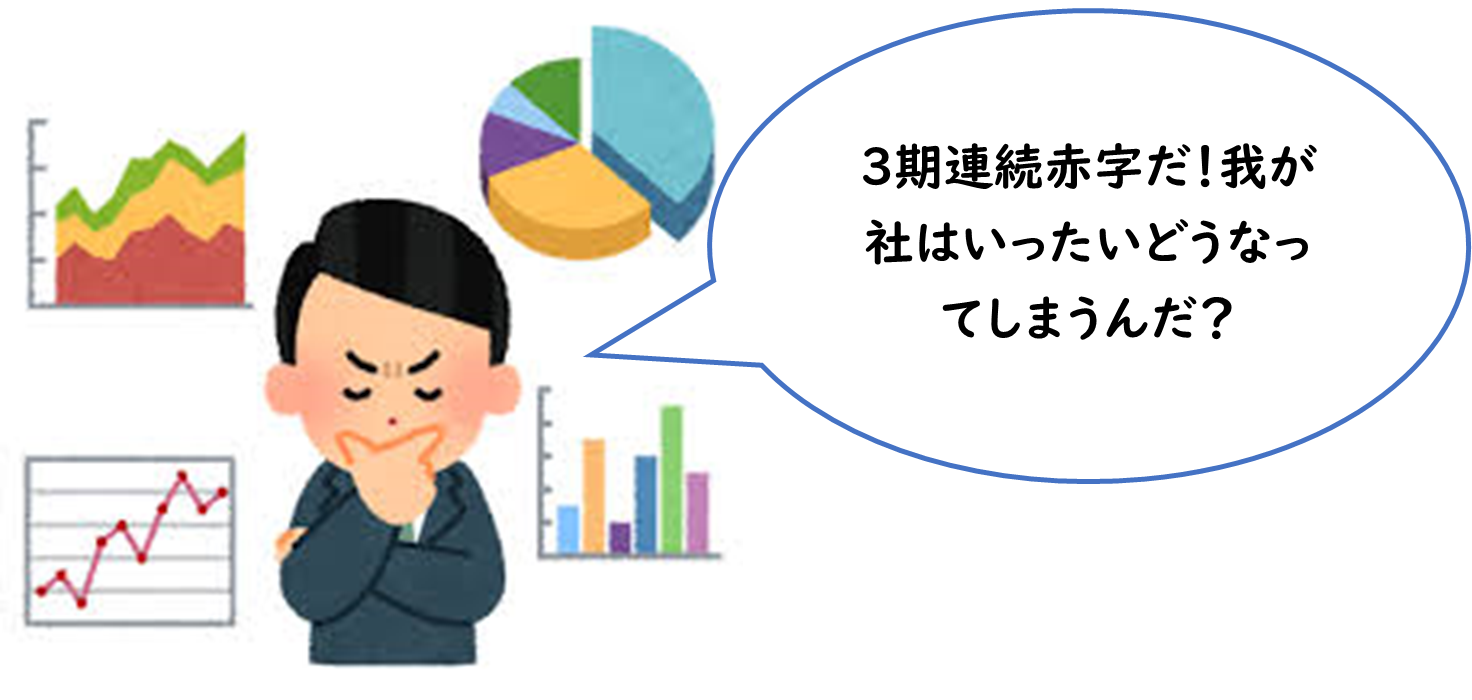
【目次】
3期連続で赤字ということは、本来であれば事業活動から資金を生み出せていないはずです。それでも会社が倒産せずに続いているのは、何らかの形で赤字による資金不足を補填し続けているからに他なりません。
内部・外部からの資金補填
その資金源としては、主に以下のようなものが考えられます。
1. 経営者(役員)からの投入: 役員報酬の未払いや削減、個人の預貯金・資産の投入(役員借入金の増加)。
2. 過去の銀行融資: 業績が悪化する前に受けた融資の残りで資金繰りをつないでいる。
3. 公的支援: 過去のコロナ関連給付金など、一時的な支援金で補填した。
4. 内部留保・資産の取り崩し: 過去の利益の蓄積(現預金)や、遊休資産(土地・有価証券など)の売却、保険の解約などで資金を捻出。
5. 支払いの猶予: 仕入先への支払遅延、税金・社会保険料の滞納や分納・猶予。
しかし、これらの方法はすべて一時的な延命策に過ぎません。 役員の個人資産には限界があり、銀行からの追加融資は困難になり、資産もいつかは尽きます。支払いを遅らせれば信用を失います。根本的な収益構造を改善しない限り、いずれ資金は完全にショートします。
[関連記事:赤字なのにお金が増えた?その理由と潜むリスク]
「3期連続赤字 どうなる?」この問いに対する現実的な答えは、会社の存続基盤が揺らぎ、利害関係者(ステークホルダー)の態度が厳しく変化していく、ということです。
銀行の融資姿勢:追加融資は極めて困難に (3期連続赤字 融資)
銀行にとって、3期連続赤字は極めてネガティブなシグナルです。
・返済能力への強い懸念: 継続的な赤字は、借入金の返済原資(利益+減価償却費)を生み出せないことを意味します。銀行は「貸したお金が返ってこないリスクが非常に高い」と判断します。
・追加融資の原則謝絶: 新規の融資はもちろん、運転資金のつなぎ融資であっても、「3期連続赤字 融資」は原則として極めて困難になります。銀行は支援から、債権保全・回収へとスタンスをシフトさせる可能性が高まります。
・支援の「選別」: 特にコロナ禍後の現在、銀行は融資先企業の「選別」を強めています。自力での改善が見込めない企業への支援は打ち切られる傾向にあります。
[関連記事:銀行が救う会社、見捨てる会社 – 融資先選別時代に備える]
[関連記事:2期連続赤字が続くと、銀行員にチェックされる決算書3つの項目]
政府方針の変更と再生計画の必須化
さらに、国の政策方針も変化しています。経済産業省・金融庁・財務省が令和6年3月に公表した「再生支援の総合的対策」では、金融機関に対し、安易な返済猶予(リスケジュール)ではなく、「実現性の高い抜本的な経営再建計画」の策定を促す方針が示されました。
これは、**「計画なきリスケは、不良債権と見なされる可能性がある」**という金融機関へのメッセージであり、今後、経営不振企業が銀行からの支援(リスケジュール含む)を得るためには、専門家(認定支援機関)の支援を受けた本格的な経営改善計画(例:405事業の活用)の策定が、事実上必須となることを意味します。3期連続赤字の企業にとっては、待ったなしの状況と言えるでしょう。
[参照リンク:金融庁 再生支援の総合的対策]
[関連記事:405事業とは?流れ・メリット・デメリットと成功の鍵]
税金・社会保険料の支払い問題
赤字が続くと法人税は発生しませんが、消費税は売上がある限り発生します(課税事業者)。しかし、資金繰りが厳しくなると、顧客から預かったはずの消費税分まで運転資金に流用してしまい、納税時期に支払えなくなるケースが多発します。滞納は延滞税だけでなく、信用失墜や最悪の場合、差し押さえに繋がります。社会保険料の支払いも同様に困難になることがあります。
資金繰りの逼迫と支払い不能リスク
売上が低迷しても、家賃や人件費(固定給部分)、リース料などの固定費はかかり続けます。入ってくるお金(売上入金)よりも、出ていくお金(固定費+変動費+借入返済)が多い状態が続けば、現預金は減少し続け、いずれ資金ショートします。資金ショートは、事実上の倒産状態です。
これを防ぐには、即効性のあるコストカット(ただし、将来に必要なコストまで削らない注意が必要)や、根本的な収益改善が急務となります。
[関連記事:【コスト削減確認シート付】営業利益マイナス。具体的なコストカット方法]
取引先(仕入先)からの信用低下
会社の経営状態が悪化していることは、日々の取引を通じて仕入先にも伝わります。大手メーカーなどが仕入先の場合、与信管理を厳格化し、保証金の積み増しを要求したり、支払いサイトの短縮(現金取引への変更など)を求めてきたりする可能性があります。これにより、仕入が困難になり、事業運営に支障をきたします。
従業員の離職リスク
経営者が隠そうとしても、会社の厳しい状況は従業員に伝わります。特に優秀な社員ほど、将来への不安から早期に転職を考え始めます。人手不足が深刻な昨今、キーパーソンの離職は、残った従業員の負担増、士気の低下を招き、事業運営をさらに困難にします。 給与遅配などが発生する段階になれば、再生は極めて難しくなります。
[関連記事:【人件費計算シート付】あなたの会社の人件費は適正か?]
3期連続赤字という現実は、経営者に対して「このまま事業を続けるのか、それとも別の道を選ぶのか」という根本的な問いを突きつけます。感情論や希望的観測ではなく、客観的な状況分析に基づいた「覚悟」と「選択」、すなわち経営者による最終的な意思決定が必要です。
現状の客観的な評価:事業継続は可能か?
まず、自社の事業に再生の可能性があるのかどうかを、冷静かつ客観的に評価する必要があります。以下の点を自問自答してみてください。外部の専門家(コンサルタントやメインバンク)の意見を聞くことも非常に重要です。
・顧客基盤: 自社の商品・サービスを支持してくれる顧客は、今後も存在し続けるか?
・事業の強み: 競合と比較して、生き残れるだけの明確な強み(技術、ブランド、サービス、立地など)はあるか?
・将来性: 市場の変化に対応し、新たな価値を生み出すための「種」はあるか?
・改善余地: コスト構造を見直し、削減できる余地は残っているか?
・人的資源: 経営者自身のリーダーシップ、従業員のスキルやモチベーションはどうか?
選択肢①:事業継続(経営改善計画の策定・実行)
上記の評価の結果、「再生の可能性あり」と判断できれば、覚悟を決めて抜本的な経営改革に取り組む道があります。そのためには、前述の通り、金融機関(銀行)も納得するような具体的かつ実現可能性の高い経営改善計画を策定し、それを断行していく必要があります。多くの場合、405事業などの公的支援制度の活用や、専門家の伴走支援が不可欠となります。
選択肢②:事業の停止(廃業・M&Aなど)
客観的に見て再生可能性が低い、あるいは経営者自身が事業継続への意欲を失っている場合は、傷がさらに深くなる前に、事業を停止する(たたむ)という選択肢も現実的に検討すべきです。単なる廃業だけでなく、事業の一部または全部を他社へ譲渡するM&Aなども考えられます。早期に決断し、計画的に進めることで、関係者への影響を最小限に抑えることができます。
早期決断の重要性
どちらの道を選ぶにしても、**最も避けたいのは「決断の先送り」**です。時間が経てば経つほど、財務状況は悪化し、打てる手は少なくなり、選択肢は狭まります。厳しい現実から目を背けず、早期に客観的な評価を行い、覚悟を持って意思決定することが、経営者の重要な責任です。
「3期連続赤字」は、会社が極めて深刻な状況にあることを示す最終警告です。「3期連続赤字 どうなる?」という問いへの答えは、銀行からの融資停止、取引条件の悪化、人材流出、そして最終的には事業継続の危機です。
この状況を打開するには、
1. なぜ3期連続赤字でも生き延びてこられたのか、その(持続不可能な)理由を認識する。
2. 銀行をはじめとする利害関係者の態度が厳しくなる現実を直視する。
3. 自社の事業継続可能性を客観的に評価する。
4. 「事業継続(抜本改革)」か「事業停止(計画的撤退)」か、覚悟を持って早期に意思決定する。
5. どの道を選ぶにしても、専門家や関係機関に相談し、計画的に進める。
ことが不可欠です。厳しい決断となりますが、未来を見据えた勇気ある一歩を踏み出すことが、経営者自身、そして関係者のためにも重要となります。
この記事が、困難な状況にある経営者の皆様にとって、現状を整理し、次の一手を考えるための一助となれば幸いです。
お問い合わせはこちらから。☟