
「複数の銀行からの融資、返済管理が大変…一本化できないかな?」
「毎月の返済額を減らしたい。融資を組み換えて期間を延ばせないだろうか?」
「銀行に融資の組み換え(巻き直し)をお願いしたら、難色を示された。なぜ?」
複数の銀行から融資を受けている経営者の方なら、返済管理の煩雑さや月々の返済負担の重さから、借入を一つにまとめる「融資 一本化」や、条件を見直す「融資 組み換え」・「融資 巻き直し」を検討したことがあるかもしれません。資金繰りを楽にするための有効な手段に思えますが、実際に銀行に相談すると、**「銀行 組み換え 嫌がる」**という反応が返ってくることも少なくありません。
なぜ銀行は、一見すると債権管理が楽になりそうな融資の一本化や組み換えに、慎重な姿勢を示すのでしょうか?
この記事では、ここ愛媛県をはじめ多くの中小企業をご支援してきたコンサルタント(元銀行員)として、融資の組み換え・一本化・巻き直しの基本的な意味合い、銀行がそれを嫌がる具体的な理由、そして、それでも実現するための方法と注意点について解説します。
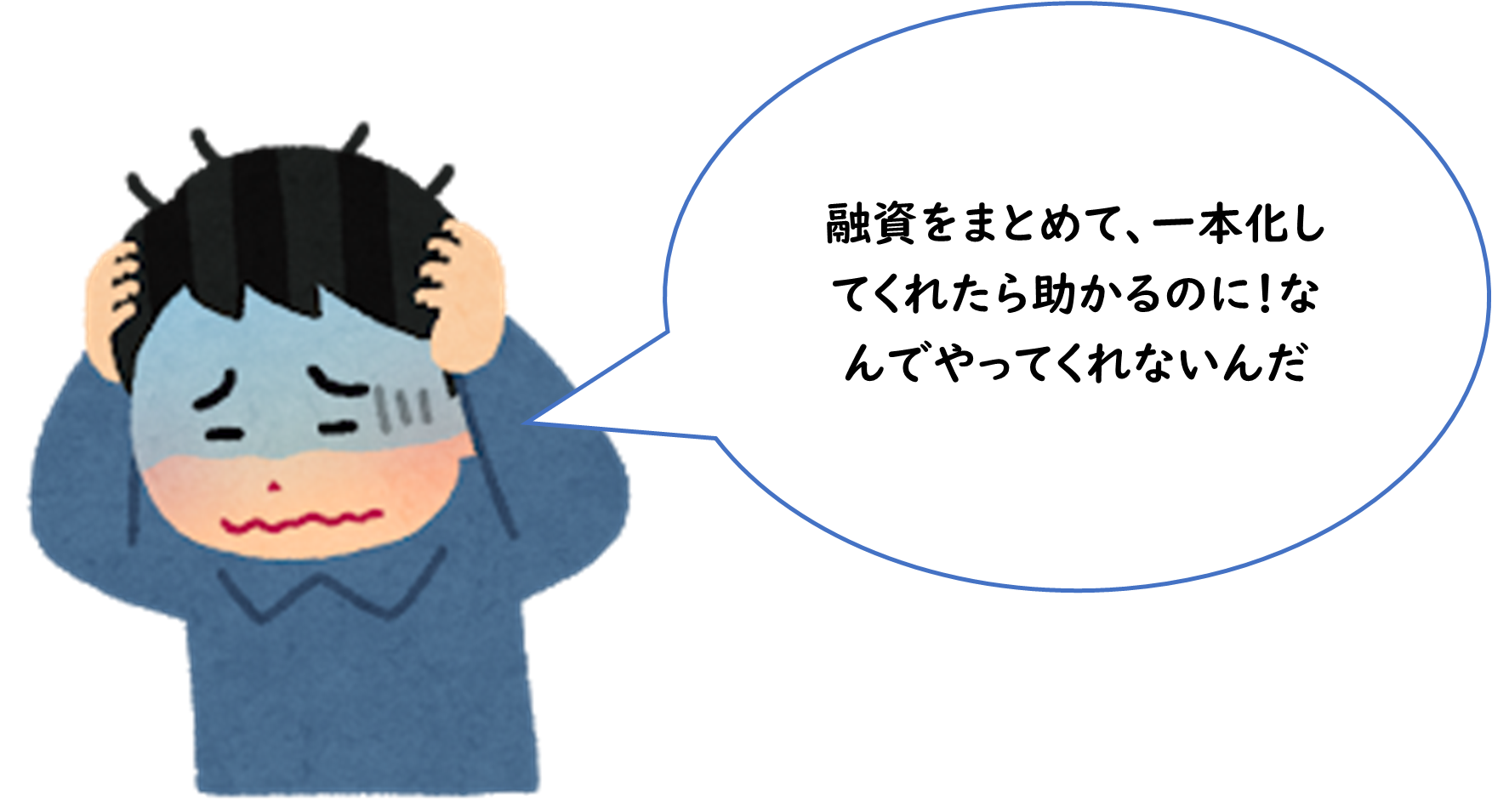
【目次】
まず、似たような言葉ですが、それぞれの意味合いを確認しましょう。
・融資 組み換え: 既存の融資の条件(金利、期間、返済方法など)を変更したり、複数の融資をまとめて新たな条件の融資に切り替えたりすること全般を指します。
・融資 一本化: 複数の金融機関や複数の契約に分かれている借入を、一つの融資契約にまとめること。組み換えの一形態です。
・融資 巻き直し: 主に、既存の融資(特に返済が進んだもの)を、新たな融資に切り替え、場合によっては融資額を当初の水準に戻したり増額したりすること。これも組み換えの一種と言えます。
経営者がこれらの組み換え・一本化・巻き直しを希望する主な狙いは、
・返済管理の簡素化: 複数の返済日や返済額を管理する手間を省く。
・月々の返済負担の軽減: 返済期間を延長することで、毎月の元利金返済額を抑え、資金繰りを楽にする。
・金利負担の軽減: より低い金利の融資に借り換える。(これは他行への肩代わりも含む)
などがあります。
経営者にとってはメリットがあるように見える融資の組み換え・一本化ですが、銀行側には慎重にならざるを得ない、いくつかの理由があります。「銀行 組み換え 嫌がる」背景を理解しましょう。
理由①:資金使途の混同
銀行は融資を実行する際、その資金が何に使われるか(運転資金なのか、設備資金なのか)という「資金使途」を非常に重視します。運転資金と設備資金では、本来、返済原資の考え方や適切な返済期間が異なります。使途の異なる複数の融資を一本化してしまうと、元の資金使途が曖昧になり、銀行は融資の適切な管理(返済状況の評価など)が難しくなると考えます。
[関連記事:借入金 長短バランス – なぜ崩れる?資金繰りを楽にする改善策]
理由②:融資形態・種類(プロパー/保証付)の混同
短期融資(手形貸付など)と長期融資(証書貸付)では、リスクの性質が異なります。また、銀行自身がリスクを負う「プロパー融資」と、信用保証協会が保証する「保証付き融資」も、銀行にとってはリスクの度合いが全く違います。
例えば、銀行にとってリスクの低い保証付き融資を、リスクの高いプロパー融資に組み替える(一本化する)ような提案は、銀行が追加のリスクを負うことになるため、まず受け入れられません。
理由③:返済期限の延長(条件緩和)に伴う問題【重要】
これが銀行が最も嫌がる理由の一つです。複数の融資を一本化し、返済期間を当初の約束よりも延長することは、銀行内部で**「返済条件の緩和(リスケジュール)」と見なされる可能性が高いです。
特に、業績が悪化している企業の返済条件を緩和した場合、その融資は「要管理債権(条件緩和債権)」などに分類され、銀行は追加の貸倒引当金を積む必要**が生じます。これは銀行の収益を圧迫します。また、一度条件緩和先に認定されると、企業側もその後の新規融資を受けるのが非常に困難になるというデメリットがあります。
そのため、銀行は安易な期間延長を伴う組み換え・一本化には極めて慎重です。多くの場合、「現状の返済を続けながら、必要であれば追加の新規融資で対応しましょう」という提案になりがちです。
理由④:担保・保証条件の変更リスク
融資の組み換えによって、担保(特に個別の融資と紐づく抵当権)の順位が変わってしまったり、有力な保証人が保証から外れてしまったりするなど、銀行にとっての債権保全(回収可能性)が悪化するようなケースでは、組み換えは認められません。
[関連記事:銀行融資と担保の関係 – 抵当権と根抵当権の違いは?]
理由⑤:業績不振企業への実質的な新規融資
融資の組み換え・一本化は、形式上、既存の融資を一度完済し、新たな融資契約を結ぶことになります。つまり、実質的には新規融資と同じ審査プロセスが必要となります。もし会社の業績が悪化している場合、銀行は新たなリスクを取ることに消極的になり、「現状維持」を選択しがちです。
銀行が難色を示すことが多い融資の組み換え・一本化ですが、全く不可能というわけではありません。いくつかの方法が考えられます。
方法①:銀行主導の提案に乗る
業績が良好な企業に対しては、銀行側から「複数の借入をまとめて、さらに追加融資も可能です」といった、自行内での有利な組み換え・巻き直しの提案がある場合があります。これは銀行にとってもメリットがある(取引深耕、金利収入増など)ため、スムーズに進む可能性が高いです。
方法②:業績改善を前提とした交渉
現在、業績が厳しい状況であっても、実現可能性の高い経営改善計画を策定し、将来の収益力回復と返済能力向上を具体的に示すことができれば、銀行も支援の一環として融資の組み換え・一本化(特に返済期間の延長=リスケジュール)に応じる可能性があります。405事業などの公的支援制度を活用して専門家と計画を練り、銀行と交渉するのが有効な手段です。
[関連記事:405事業とは?流れ・メリット・デメリットと成功の鍵]
方法③:他行による肩代わり(最終手段・要注意)
これは「奥の手」とも言えますが、リスクも伴う方法です。現在の取引銀行が組み換え・一本化に全く応じてくれない場合、他の銀行に相談し、既存の借入をすべて肩代わりしてもらうという選択肢です。
新しい銀行は、取引を獲得するために、魅力的な条件(低金利、融資の一本化など)を提示してくる可能性があります。
・注意点: ただし、融資 肩代わりを実行すると、元の銀行との関係はほぼ確実に悪化・途絶します。将来、その銀行からの支援は期待できなくなると覚悟する必要があります。メリットとデメリットを慎重に比較検討してください。
[関連記事:融資 肩代わり – 銀行が嫌がる理由と影響は?]
[関連記事:メインバンクを変更する方法と注意点]
安易に融資の組み換え・一本化を進める前に、以下の点も考慮しましょう。
・本当に資金繰りは楽になるか?(総返済額の増加): 返済期間を延ばせば月々の返済額は減りますが、利息を含めた総返済額は増加する可能性があります。
・銀行との関係性への影響: 無理な要求は、銀行との信頼関係を損なう可能性があります。特に肩代わりは慎重に。
・手数料や諸経費: 組み換えに伴い、新たな契約手数料や登記費用などが発生する場合があります。
複数の銀行融資をまとめたい、返済を楽にしたいという経営者の思いは自然なものです。しかし、融資の一本化・組み換え・巻き直しは、銀行側にとっては様々なリスクや内部的な手続きの問題があり、「銀行 組み換え 嫌がる」ケースが多いのが実情です。
実現のためには、
1. なぜ銀行が難色を示すのか、その理由を理解する。
2. 自社の状況(業績、財務内容)を客観的に把握する。
3. 業績改善計画など、銀行を説得できる具体的な材料を用意する。
4. 場合によっては、他行への肩代わりも選択肢に入れつつ、リスクを十分に検討する。
といった戦略的なアプローチが必要です。
まずは自社の借入状況を整理し、返済負担が過大になっていないか、改善の余地はないか、信頼できる専門家や取引銀行に相談してみてはいかがでしょうか。
この記事が、貴社の融資戦略と資金繰り改善の一助となれば幸いです。
ご相談・お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。☟