
これまで3回にわたり、銀行が中小企業の決算書のどこに注目しているのかを、貸借対照表、損益計算書、販売管理費に焦点を当てて解説してきました。最終回となる今回は、これらの財務諸表の内訳を示す勘定科目内訳明細について、銀行員がどのように分析し、何を読み取ろうとしているのかを、中小企業支援を行う経営コンサルタントの視点から解説します。銀行が決算書のどこを見るのか、その理解をさらに深めていきましょう。
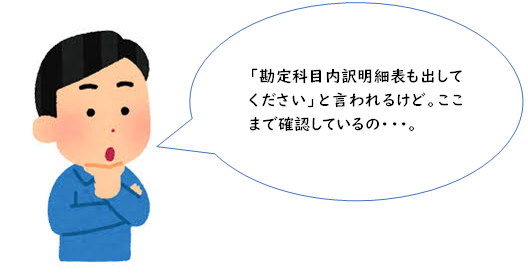
【目次】
銀行に決算書を提出する際、勘定科目内訳明細の提出を求められることがほとんどです。これは、勘定科目内訳明細がないと、銀行は貸借対照表や損益計算書の各科目の詳細な内訳を把握できず、より深い分析を行うことが困難になるためです。銀行員は、この明細を通じて、各勘定科目の実態やリスク、将来性を評価しようとしています。
貸借対照表の各科目の内訳である勘定科目内訳明細からは、以下のような点がチェックされています。
1. 現預金の内訳:メインバンクとの関係性(銀行 決算書 見方)
銀行員は、現預金の内訳を確認し、自行と他の銀行との預金残高のバランスを見ます。メインバンクであるにもかかわらず、期末の預金残高が他の銀行よりも少ない場合、「なぜですか?」と質問されることがあります。また、他行との定期性預金のバランスも確認しています。
銀行員の感覚としては、融資残高が多い銀行がメインバンクであり、預金も当然多くあるべきという意識がありますが、経営者の意識とは必ずしも一致しないことがあります。これは立場による違いと言えるでしょう。
【関連記事】メインバンクの概念について~企業側と銀行側の考え方の違い~:企業と銀行のメインバンクに対する考え方の違いを解説しています。
2. 売掛金の内訳:不良債権の可能性を探る
売掛金の内訳を確認し、過去3期分のデータと比較して、毎年同じ金額で残高が上がっている取引先がないかをチェックします。これは、回収が進んでいない不良債権の可能性があるためです。
3. 受取手形の内訳:手形サイトと不渡りの有無
受取手形の内訳では、手形の振出先と**手形のサイト(入金までの期間)**を確認します。また、不渡りとなっている手形がないかも重要なチェックポイントです。
4. その他の流動資産の内訳:不良資産の隠匿に注意(銀行 不良資産判定)
その他の流動資産に計上されている仮払金、長短貸付金、未収入金、投資有価証券などは、不良資産が隠れているケースが多いため、念入りにチェックされます。
5. 支払手形の内訳:長期化による実質的な借入の疑義
支払手形の内訳では、手形の振出先と手形のサイトを確認します。手形サイトが長期化している場合は、通常の仕入代金の支払いではなく、手形振出先からの実質的な融資を受けているのではないかと疑念を持たれることがあります。
6. 借入金の内訳:金融機関との取引状況(銀行 勘定科目内訳明細 チェックポイント)
借入金の内訳では、自行と他の銀行との借入残高のバランスを見ます。他行の金利水準や、他行の借入残高の急な増減も確認します。他行の借入が増加している場合は、その要因についてヒアリングが行われることがあります。逆に、他行の借入が減少している場合は、資金引き上げの動きがないか注視します。銀行は、借入金の状況を通じて、他行との取引動向を常に把握しようとしています。
【関連記事】【なぜ銀行は他行の融資条件を聞く?】複数行取引での情報開示と心構え(2025年版)
損益計算書や販売管理費の内訳である勘定科目内訳明細からは、以下のような点がチェックされています。
1. 売上の内訳:コア事業と収益構造の分析
売上高の内訳として、事業別売上や商品別売上を確認し、企業のコア事業が何か、そしてその推移がどうなっているかを分析します。
2. 役員報酬の内訳:親族への偏りと適正性の判断
役員報酬の内訳では、親族間の報酬額と、親族以外の役員への報酬額を確認します。役員報酬の決定が、経営の実態に基づいているか、適正な水準であるかを判断しようとしています。
3. 特別利益・特別損失の内訳:一過性損益と経常的な収益力の区別
特別利益・特別損失の内訳を確認し、それが今期だけの一過性のものなのか、それとも恒常的に発生するものなのかを判断します。これにより、企業の真の収益力を把握しようとしています。
4回にわたり、「銀行員は決算書のどこを見ているか」について解説してきましたが、今回ご紹介したのはほんの一部です。銀行員は、企業の決算書をより深く、詳細に分析しています。データ分析も高度に進んでいます。
かつて、私が銀行員として営業をしていた時、お客様から「〇〇銀行用」と手書きされた決算書を渡されたことがあります。その企業は、複数の銀行に対して別々の決算書を作成しており、誤って異なる銀行に渡してしまったという笑えない話です。このような行為は、銀行からの信頼を大きく損なうことにつながります。
やはり、銀行に対しては正直に経営状況を開示することが最も重要です。
本シリーズを通じて、銀行が企業の決算書のどこに注目し、どのように分析しているのかをご理解いただけたかと思います。銀行の視点を理解し、日々の経営に活かすことで、金融機関との良好な関係を築き、円滑な資金調達につなげることが可能になります。
貴社の勘定科目内訳明細、銀行の視点でさらに深く分析しませんか?
中小企業支援を行う経営コンサルタントの私が、貴社の勘定科目内訳明細を銀行の視点から詳細に分析し、潜在的なリスクや改善点について具体的なアドバイスを提供いたします。
【無料個別相談のご案内】
「銀行が注目する勘定科目のポイントを具体的に知りたい」
「決算書の見せ方を改善し、銀行からの評価を高めたい」
「今後の資金調達に向けて、財務戦略を強化したい」
上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の初回無料個別相談をご活用ください。経験豊富なコンサルタントが、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、具体的な解決策をご提案いたします。
貴社の更なる発展のために、私たちがお手伝いできることがあれば幸いです。まずはお気軽にお問い合わせください。
財務改善、経営力強化に関するお問い合わせは、こちらからどうぞ☟